転職活動をしていると、必ずといっていいほど聞かれる質問があります。
「あなたは何ができますか?」
管理職経験がある人が、そこでつい口にしてしまう答えのひとつが、
「部長ができます」。
ところが、この答えは採用の現場ではあまり評価されません。
時には「それってつまり何もできないってことですよね」と受け止められてしまうことすらあります。
特に近年は「ジョブ型雇用」の傾向が強まっており、企業は特定のスキルや専門性を求めがちです。
「部長ができます」だけでは、専門性が見えにくく、どうしても評価されにくいのです。
でも、ここに大きな誤解があります。
実は「部長ができる」というのは、とても高度な専門性を持っている証拠なのです。
今回は、なぜ「部長ができます」がマイナスに映りがちなのか、そしてどう伝えれば強みとして評価されるのかを整理していきます。
「部長ができます」が評価されにくい理由

まず、人事や採用担当者の視点で考えてみましょう。
「エンジニアです」と言われれば、「どの言語や技術に強いのか?」と専門性をイメージできます。
「営業です」と言われれば、「どんな業界で、どれくらいの売上を上げてきたのか?」を聞きたくなります。
ところが「部長ができます」と言われても、具体的に何ができるのかが全く見えてきません。
採用側からすると、こんなふうに見えてしまうのです。
「この人は結局、専門スキルがないのでは?」
「権限で動いてきただけで、実務は部下に丸投げしていたのでは?」
「管理職だから偉そうにしているだけで、手を動かせないのでは?」
つまり「専門性のない人」「部下に丸投げする人」というネガティブなラベルが貼られやすいのです。
ここにこそ、「部長経験があるのに評価されにくい」大きな理由があります。
実際の部長の仕事は「丸投げ」ではない
では、実際に部長がやっている仕事はどうでしょうか。
本当のところ、部長の役割は「部下に丸投げ」どころではありません。
むしろ、専門職では対応できない領域を引き受けるポジションなのです。
〇経営戦略を理解し、自部門の目標に落とし込む
〇部署の業績責任を担い、数字を管理する
〇人材を育成・評価し、次世代の力を引き出す
〇複数部署の利害を調整し、社内外と交渉する
〇白黒つけにくい状況で意思決定を下す
〇変化の中で自部門の将来像を描く
部長の仕事は「専門スキルを持った部下に任せる」だけでは到底成り立たないことが分かります。
むしろ、専門家を理解し、まとめ、全体を動かすという独自の専門性が必要なのです。
部長に求められる専門性とは?
部長に必要な能力を整理すると、次のように言い換えることができます。
戦略的思考力:経営方針を理解し、部署戦略に翻訳する力
分析力:データ・環境・人材を客観的に把握する力
意思決定力と胆力:正解のない中で判断し、責任を取る力
ロジカルシンキング:複雑な情報を整理し、筋道を立てて方向を示す力
コミュニケーション力・調整力:上層部、他部署、顧客、部下との橋渡しをする力
リーダーシップ:人をまとめ、動機づけ、方向性を示す力
人材育成力:部下を育て、組織を強くする力
広い視野:専門領域を超え、全体最適を考える力
こうして分解すると、「部長ができます」という一言が、いかに多くの能力を内包しているかが見えてきます。
つまり「部長ができる」とは、「管理の専門職ができる」ということなのです。
「部長ができます」をアピールに変える3ステップ

では、転職の場でどう伝えればよいのでしょうか。
ここでは3つのステップを紹介します。
1.経験をスキルに翻訳する
「部長」という肩書きではなく、「そこで何をしたか」「どんな能力を使ったか」を言葉にする。
例:
- 「20名の部下を率いた」
→「20名規模の組織運営スキル」「人材育成と業績管理の経験」 - 「部署を運営した」
→「部門横断プロジェクトを推進し、コスト△%削減を実現」
2.エピソードで具体化する
スキルだけでは抽象的なので、具体的な成果や数字を添える。
例:
- 「評価制度を導入し、部下の昇進者数を前年比150%に増やした」
- 「他部署と連携し、プロジェクトを予定より3か月早く完了させた」
3.職位ではなく能力で自己紹介する
面接や経歴書では「部長です」ではなく「〇〇の能力を活かしてきました」と伝える。
👉 「私は管理職として、調整力と意思決定力を活かして組織をまとめてきました」
👉 「人材育成に力を入れ、離職率を30%改善しました」
実際の転職活動での使い分け
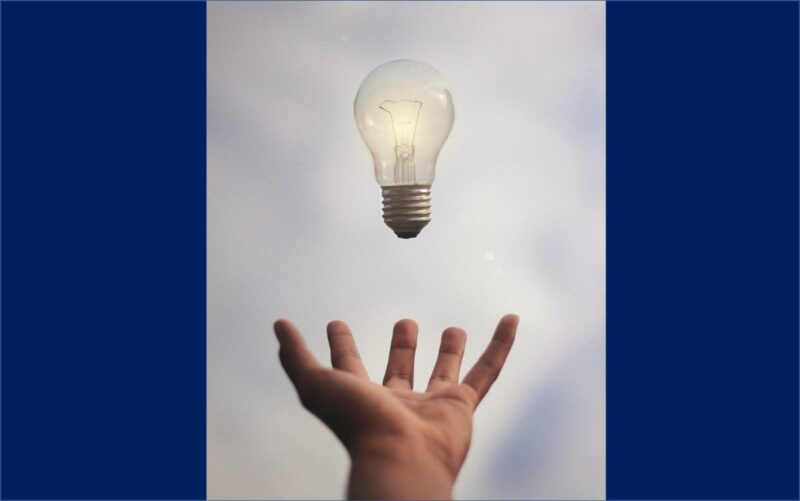
職務経歴書
職務経歴書では、単に「部長」と肩書きを書くだけでは不十分です。
「どんな規模の組織を率いたのか」「どんな成果を上げたのか」を、スキルや実績に翻訳して書く必要があります。
例を挙げると
悪い書き方:「部長として組織を統括」
良い書き方:「部長として20名規模の組織を統括。評価制度を改善し、離職率を30%改善。コスト削減を実現し、年間500万円の経費圧縮に成功」
数字や客観的な成果を入れることで「この人がやってきたこと」が読み手に伝わりやすくなります。
また、「人材育成」「調整力」「意思決定」等のキーワードを盛り込むと、管理職としての専門性が際立ちます。
面接
面接では、抽象的な「マネジメント経験があります」だけでは弱いです。
具体的なエピソードを、STAR法(Situation→Task→Action→Result)で整理して話すと効果的です。
STAR法が初めての方もいると思うので具体例を挙げます。
S(状況):部署の離職率が高く、チームの士気が下がっていた
T(課題):組織を安定させ、業績改善につなげる必要があった
A(行動):評価制度を見直し、1on1を導入。部下の意欲を引き出す仕組みを整えた
R(結果):離職率を前年比30%改善。業績も前年対比110%に改善
「成果」とその過程において「具体的に何をしたか」を説明できると、採用側は「この人なら同じように再現できる」とイメージできます。
志望動機
志望動機では「部長をやってきました」ではなく、相手企業の課題に自分の経験を結びつけることが重要です。
NG例(抽象的すぎる)
「これまで部長としてマネジメント経験を積んできました。その経験を御社でも活かしたいと考えています。」
→ これでは「何を活かすのか?どう役立つのか?」が不明確で弱い。
より具体的に…OK例(自分の実績と相手の課題を結びつける)を言うと…
「私はA社にて人事制度の見直しと1on1面談を導入し、離職率を前年比30%改善した経験があります。御社も若手社員の定着が課題と伺っておりますので、これまでの施策を活かし、組織の安定化に貢献できると考えています。」
「私はA社で複数部署を横断するプロジェクトを統括し、予定より3か月早く完了させた経験があります。御社の新規事業立ち上げにおいても、部門間の調整やスピード感ある推進に寄与できると確信しております。」
このように 「私の経験(事実) → 貴社の課題(理解) → 具体的にどう役立つか(貢献)」 という流れをつくると、相手は「この人なら課題解決に効きそう」とイメージしやすくなります。
まとめ:「部長ができます」は高度な専門性

「部長ができます」だけだと、人事からは「専門性がない人」「部下に丸投げするだけの人」と見られがち。
でも、実際には部長職には高度な専門性が求められています。
〇経営と現場をつなぐ力
〇複数の専門家を理解し、まとめる力
〇不確実な状況で判断し、組織を動かす力
大切なのは、それを「部長」という肩書きではなく、能力やエピソードに翻訳して伝えること。
それができれば、「部長経験」は転職市場で強力な武器になります。
「部長ができます」という一言は、決して空虚なものではありません。
それは「組織を動かす専門性を持っている」という証拠なのです。
【広告】
お手軽に転職についてご自身の強みを発見したい方、お手伝いいたします。
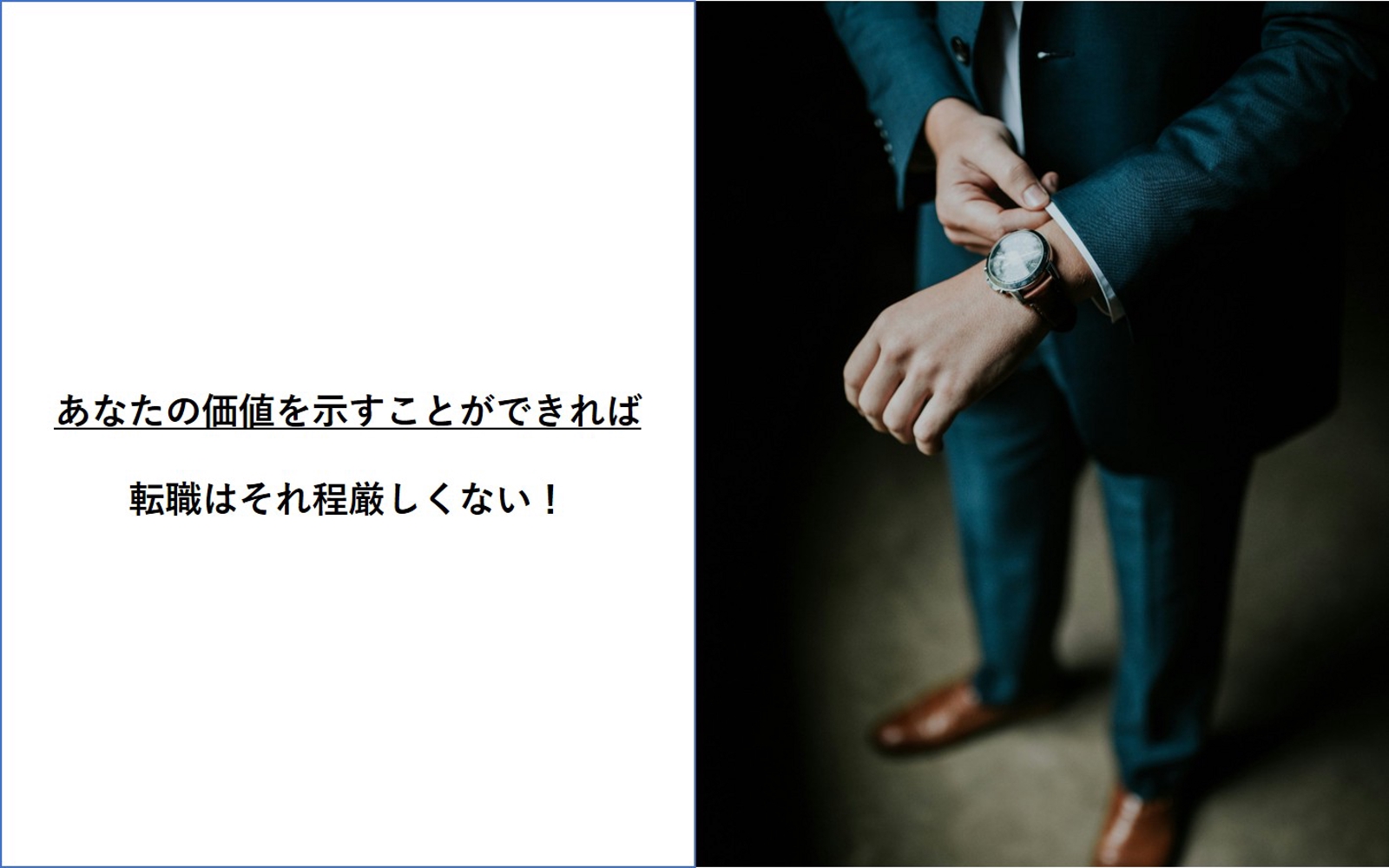
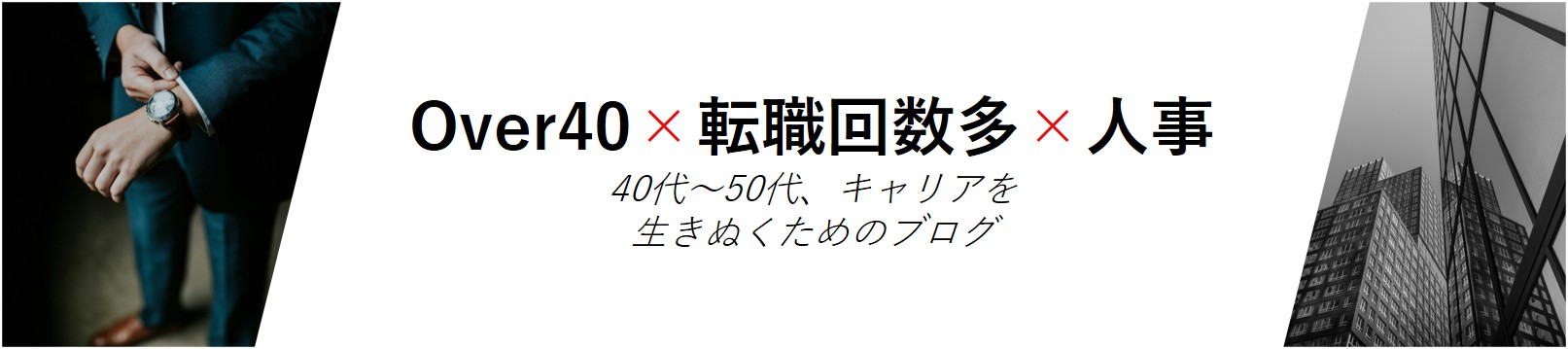
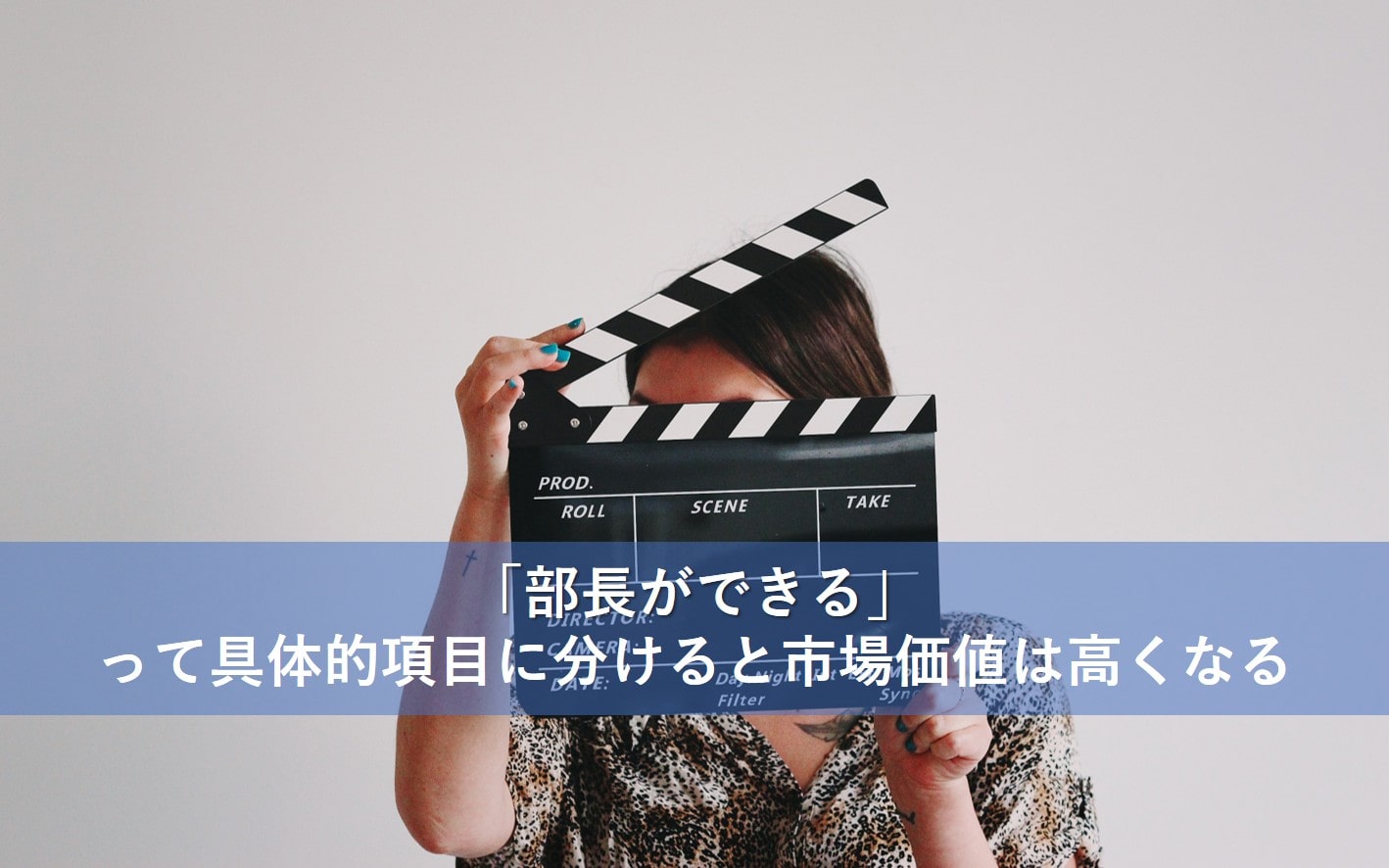



コメント