そんなことはありません。
人の好みは十人十色!会社を選ぶ理由も様々です。
会社に入る募集人数だけそろえれば良いのだから万人受けする必要もありません。
自社にヒットする人だけから興味を持ってもらえれば十分採用は成功できます。
採用に苦しむ採用担当者に向けて『等身大の採用手段』で採用を成功させる方法を記事にしました。
等身大の採用活動をするメリット

『等身大で採用をする』とは、自社を実際以上に良く見せるのではなく、ありのままの姿で採用活動を行う事。
ミスマッチを減らし、長期的に会社と求職者にとってプラスになるアプローチができます。
採用をする時、有名な会社の福利厚生、教育制度、採用費のかけ方を成功事例として参考にしがち。
しかし、まねができないことも多いし、応募者の好みも千差万別。
有名な会社を参考にしてもあまり良いことはありません。
一方で会社が等身大で自分らしさを出した場合、以下のメリットが期待できます。
1.ミスマッチの防止
実際の職場環境や文化をありのまま伝えることで、入社後のギャップを減らせる。
2.早期退職の抑制
リアルな情報を得て入社するので、定着率が向上する。
3.エンゲージメントの向上
会社の魅力を理解して応募する人が増え、意欲の高い人材が集まる。
4.採用ブランディングの向上
『正直に伝えること=誠実な採用活動』と言うことで『信頼される会社』と評価が高まる。
結果として自然と応募者が増える。
名もない会社が大手の会社を差し置いて多くの候補者に恵まれている例も少なくありません。
それは背伸びせずに等身大の採用をしているから。
飾らず等身大で採用するメリットは多くあります。
背伸びをして採用をしした時のデメリット

会社を良く見せようと実態以上に魅力的に見せたり、不都合な情報を隠した場合のデメリットは大きいです。
具体的な例は以下の通り。
1. 早期離職の増加
実際と異なる職場環境や業務内容の説明は入社時に『こんなはずじゃなかった』と後悔を促します。
結果として、短期間で退職する人が多くなり、採用にかけた時間とお金は無駄におわることも。
2. 企業の信頼低下
SNS等で求職者同士の情報共有は活発化しています。
背伸びした採用が「話が違った」「入社前の説明と違う」とネガティブな評判の火種になる可能性は低くありません。
一度悪評が広まると、次の採用活動に支障が出ることも往々にしてあります。
3. 社員のエンゲージメント低下
「入社前に聞いていた話と違う」と感じた社員は、モチベーションが下がりやすくなります。
「会社に騙された」という気持ちは、仕事への熱意を下げ、最低限の業務しかこなさなくさせます。
場合によっては会社と言う船底に穴をあけようとする人も。
4. 採用コストの増加
早期離職が増えると、また新たに人を採用しなければなりません。
求人費、面接にかかる時間、新入社員の教育コスト等企業の負担が増します。
5. 組織文化の悪化
『だまされた』と感じた人は会社の風土を乱す行為を行います。
「採用時にうそをついてもいい」という風潮が社内に広がると、組織全体の倫理観も低下。
結果、社員同士の信頼関係も薄れ、企業文化が悪化することにつながります。
6. 本当に合う人材が採用できない
企業の実態を正直に伝えないと、候補者も本当に自分に合っているか判断できません。
逆に合わない人が『自分にふさわしい』と思い応募することも。
スキルや価値観がミスマッチな人材ばかりが集まり、結局「長く働ける人」が見つからない状態になります。
結論として、背伸び採用は、長期的に会社と候補者に悪影響を与えます。
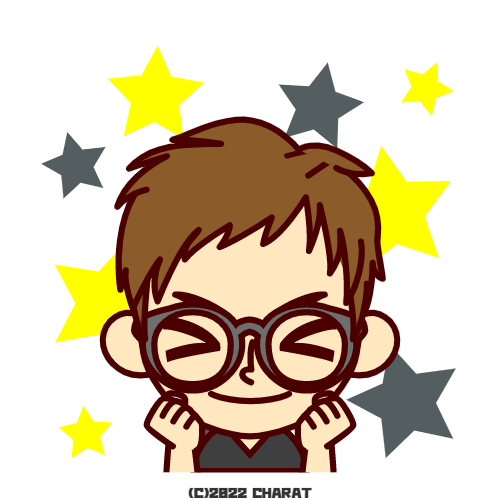
等身大の情報を伝え、会社に合った人を採用することが、成功につながります。
等身大の採用活動を実現する方法

等身大の採用は「ありのままを伝える」事なのですが、具体的に何をするのかをまとめると以下のとおり。
〇ありのままの環境を伝える
〇現場社員の声を届ける
〇過剰な演出を避ける
〇選考プロセスでも正直に伝える
〇入社後のギャップを埋める
ありのままの職場環境を伝える
〇エージェントや求人サイトで実際の働き方や文化を正直に伝える。
〇具体的なエピソードを紹介する
良い事も悪い事もありのままの環境を伝えます。
特に具体的エピソードはどのような説明より雄弁に職場の雰囲気を語ります。
「良く見せたい」と思う気持ちはあるかもしれませんが、良い事だけだと却って疑わしいです。
説明する側が悪いと思う事も候補者にとっては「自分が活躍するための場」と前向きな解釈をすることも多々。
ありのままの職場環境を伝えましょう。
現場社員の声を届ける
〇社員インタビューや座談会を活用し、リアルな働き方を発信する。
〇良い事だけでなく失敗談や苦労話を含めよりリアリティを求める。
一緒に働く人の声は候補者に入社後のイメージ情勢に最適。
また、ネガティブな事を伝えるのはとても大切です。
良い事だけを聞くと却って怪しく聞こえますが、ネガティブ情報によって現実味が増し、信頼を得られます。
実際候補者の中には不安払しょくのため、ネガティブ情報を聞いて大丈夫そうかを確認する人も。
職場の生の声は大きな武器になります。
過剰な演出を避ける
〇SNSやホームページの写真や動画は加工しない
〇ありのままのオフィス風景や仕事風景を見せる
過剰な演出はなるべく避けます。
最近では、SNSやホームページの写真の加工もしやすくなりました。
しかし加工は、面接に来た時にばれます。
オンライン面接だけで内定を出して入社となった場合、違和感を感じた候補者から「転職会議」等掲示板に書き込まれかねません。
書き込みは、採用をする側の想像よりはるかに影響大!
他の候補者の辞退率に響きます。
過剰な演出は避けありのままを見せましょう。
選考プロセスでも正直に伝える
〇面接時に『実際の職場の雰囲気』『求める人物像』は率直に伝える
〇ポジティブな内容だけでなく『向いていない人』についても説明する。
選考途中、特に面接は相手の顔が見えてしまうので、なるべく穏便に済ませたいものです。
また、候補者からの辞退はなるべく避けたいもの。
しかし、正直に伝えない延命措置をしたところでお互いの時間を無駄にするだけです。
逆に、カルチャーフィットの要素を含む会社の特徴を伝えることにより合う候補者にはフックになる事もあります。
欲しいのは会社に合う人なので万人受けしない事を恐れずありのままを伝えましょう。
入社後のギャップを減らす工夫をする
〇職場見学の機会を設ける
選考中・内定後どちらでも良いのですが、職場見学など候補者に見せることは大きな武器になります。
「きれいなオフィスではないし…」と心配するかもしれませんが、特にきれいである必要はありません。
実物を見せて「ここで働く」イメージを持たせた方が意向アップにつながりやすいです。
また、見られることが職場環境の改善につながる事もあります。
ありのままの職場を見せるのも有効です。
等身大の採用方法を実現するための準備

等身大の採用方法を実行するには大きく2つの事が必要です。
〇自分の会社を客観的に見る
〇万人受けを狙わない
自分の会社を客観的に見る事はその中にいては難しいです。
だから外から来た人に採用をさせるのが理想。
しかし、会社の方針や、リソースもあり非常そう簡単にはいかないのも事実。
だから、採用担当が取るべき方法をお伝えします。
中途入社者の声を聴く
採用担当が中途入社者であれば、その人が今までいた会社と比較して説明ができます。
しかし、そうでない場合は、中途者の声を聴くとよいです。
中途者は、他社から入社をした人:その会社を比較検討の末選んだ人。
比較検討の際、不安に思ったことや、前の会社と比較して良い所、悪いところを説明可能。
採用担当としては、候補者にアピールしたいし、意図しない事は言って欲しくないものです。
しかし、だからこそリアルに実情が伝わります。
中途者に遠慮なく話してもらう事こそが、等身大採用の準備としては重要です。
万人受けを狙わない
等身大の採用をする際、万人受けは狙いません。
万人受けを目指すと当たり障りのない事が多くなります。
つまり、会社の特徴が無くなり、候補者の立場で言うと、「良い会社だけどこの会社でなくても良い」
例えると、恋愛対象にならない「良い人」どまりになります。
また、金とリソースの有る大企業と同じことをしないといけなくなるので、負担増は避けられません。
背伸びをしたところで大企業の水準にはと届かない事も多いです。
会社の特徴を認め、100人中90人には興味を盛られなくても10人の大ファンを狙うことが大切。
万人受けは狙いません。
まとめ

等身大の採用活動を行うことで、無理に魅力を盛らなくても、企業に合った人材が自然と集まるようになります。
一方で会社を良く見せようとすると採用がしずらくなるだけでなく会社内外の評判も落とすことに。
だから採用は「等身大」の採用がお勧め!
具体的には飾らずありのままを伝える。社員の声や会社の風景をフィルターなしで伝えます。
そのための準備として、「中途者から見た客観的な意見」や「万人受けを目指さない勇気」が必要です。
もし採用活動について具体的な課題があれば、さらに深掘りしてアドバイスできますよ!
ぜひお問い合わせください。
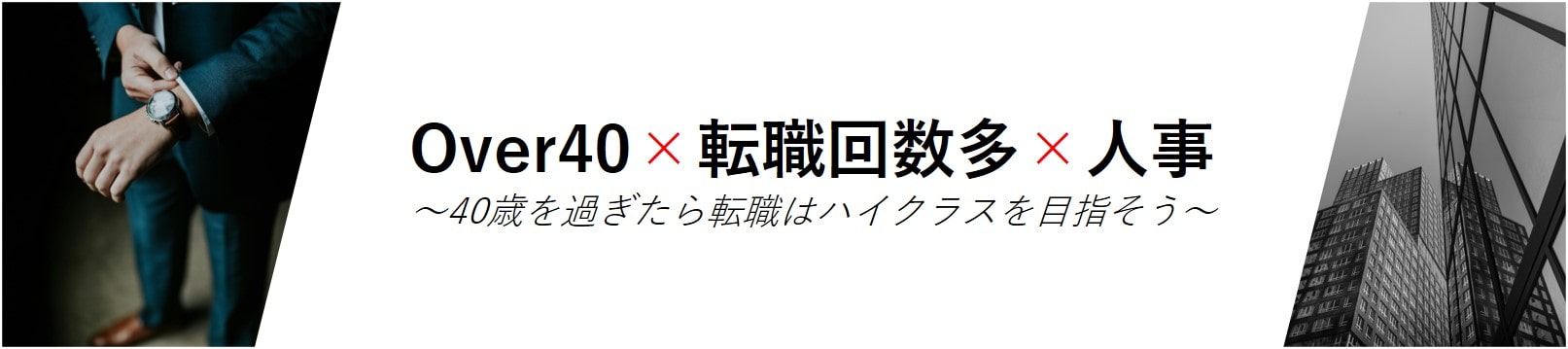



コメント