その疑問に回答します。
専門職は専門性を武器に市場価値を上げていく職職種、資格は大切と言うことはイメージできると思います。
しかし自分の専門性に合った資格は『何』で『どう勉強』すればよいか?は見つけにくいです。
そこで、今回は専門性を高めるために鍛えるべきスキルとそこに見合った資格の見つけ方、勉強の仕方について記事にしました。
この記事が参考になれば幸甚です。
鍛えるべきスキルの種類について

スキルの種類には大きく分けて2つあります。
1つは、汎用スキル、もう1つは専門スキルになります。
| 汎用スキル | 論理的思考や、コミュニケーション力等どの職種でも通用するスキル |
| 専門スキル | 専門分野の知識や独自の経験など一定の職種や一定の専門家にのみ通用するスキル |
汎用スキルはどの仕事にも活かせるので習得は必要です。でも、専門職にとってはこれだけでは足りません。
専門職は自分の専門性に根拠が必要です。
専門性に根拠があるメリットは以下のとおり
また、『あなたは何ができますか?』と聞かれた際、『●●ができます!』と言うと思いますが、資格名が大きな根拠となり面接官からの信用が得られます。
資格取得のため勉強した知識や問題解決能力は専門職としての大きな武器。
専門職として生きていくならば、専門スキルを鍛え資格を取得することは必須です。
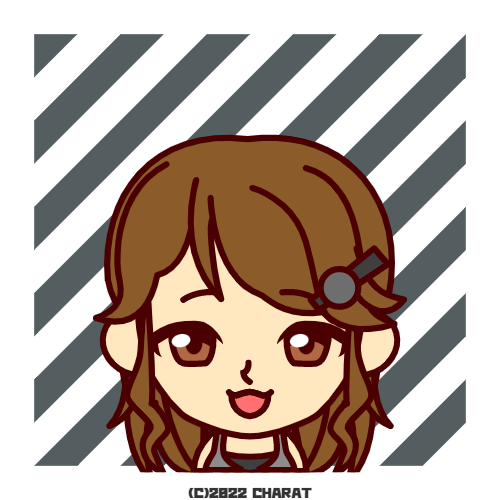
とはいえ、自分の仕事にあった資格ってどう探せば
いいかわからないですよね。
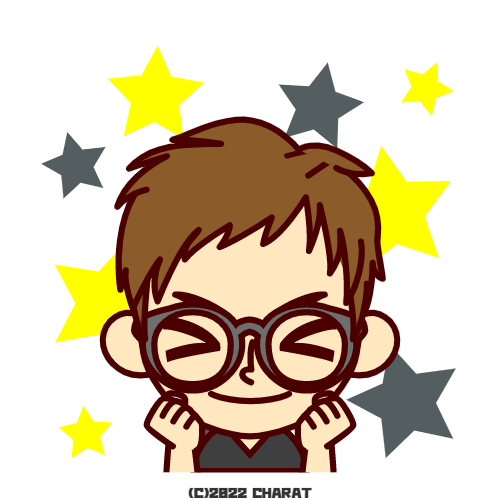
今日は自分の専門性を高める資格はどう探してくのか、
そしてどう勉強をしていくのかを紹介します。
資格を取るための勉強時間
一般的に権威性のある難しい資格を取るために必要な勉強時間は以下のとおり。
| 番号 | 資格名 | 合格率 | 一般的に必要とされる勉強時間 |
| 1 | 司法書士 | 4~5% | 3000時間 |
| 2 | 不動産鑑定士 | 5~6% | 2000時間~4000時間 |
| 3 | 中小企業診断士 | 3~8% | 1000時間 |
| 4 | 社会保険労務士 | 6~7% | 1000時間 |
| 5 | 弁理士 | 6~9% | 3000時間 |
| 6 | 公認会計士 | 7~11% | 3000時間~4000時間 |
| 7 | 一級建築士 | 10% | 700時間~1500時間 |
| 8 | 行政書士 | 11~15% | 600時間~1000時間 |
| 9 | 宅建 | 15~17% | 300時間~400時間 |
| 10 | 税理士 | 14~20% | 4000時間 |
一方で難易度の高くない資格の一般的勉強時間は以下のとおり
| 番号 | 資格名 | 一般的に必要とされる勉強時間 |
| 1 | 簿記3級 | 150時間~200時間 |
| 2 | ITパスポート | 100時間 |
| 3 | ファイナンシャルプランナー3級 | 30時間~120時間 |
| 4 | MOS | 40時間~80時間 |
| 5 | 危険物取扱者 | 50時間 |
| 6 | 秘書検定3級 | 20時間~40時間 |
資格により必要とされる勉強時間は大きく変わります。
やりがちだけどやってはいけない資格の選び方

資格の勉強をする際、資格選びは非常に重要!
だけど、注意すべき事は2つの誤った認識だけです。
その2つの誤った認識は一般的に「良いと思いがちのこと」。
この2つの事を注意して、自分に役立つ資格選びからスタートしてください。
必ずしも難しい資格が市場価値を高めるわけでは無い事を知る
「資格の勉強」と言うと「将来の為難しい資格を取っておきたい!」と思いますよね。
でも、実際転職に必要なのは、仕事に直結することです。
人事の場合、頑張って合格率10%前後の行政書士を取っても転職の場では評価はされません。
逆に合格率50%前後の衛生管理者を取った方が評価は高いです。
衛生管理者は市販の教科書で1か月も勉強すれば取れる資格!独学で十分取得可能になります。
難しい資格が市場価値を高めるわけでは無い事を知っておきましょう!
講座参加が義務の資格を選ばない
一般的に権威のある資格の中には講座参加が義務のものもあります。
例えば、産業カウンセラーの受験資格はざっくり言うと以下のとおり。
〇協会が行う産業カウンセリングの学識及び技能を修得するための講座を修了すること
〇大学院・大学で一定の教科の履修をしていること
社会人になってからその資格に興味を持った人は、指定の講座を受けないと受験資格が得られません。
独学で資格を得る事はできません。
仕事で「働く人たちが抱える問題を、心理的側面から援助したい!」という事であれば以下の資格も存在します。
産業心理カウンセラー(JADP認定)
EPAメンタルヘルスカウンセラー(EMCA認定)
メンタルケアカウンセラー(文部科学省後援)
上記は数ある資格の一部ですが、人を心理的に支援する資格です。
もちろん、合格率も高く、独学可能!
目的に合わせて資格を選ぶなら、仕事に関係のない難しい資格を目指す必要はありません。
自分の専門性に見合った資格の探し方

世間的な意見に流されず自分の仕事で資格を探す
自分の仕事への必要性をまずは確認しましょう。
世間的な意見に流されず、自分の仕事への必要性に応じて資格取得を目指します。
「役立つ資格」を見て取る資格を決める方がいますが、仕事の必要性が無かった場合、使う場所がありません。
面接での優位性を考えても「何故この資格?」と聞かれた時、資格をどのように仕事に役立てるかの想像がしにくいと面接官へのアピールには弱いです。
逆に仕事に密接に関係した資格であれば仕事に役立つし、それがどんなにマイナーな資格でも面接官に響きます。
世間的には「役立つ」と言われているけど仕事に関係ない資格よりマイナーで仕事に密接な資格の方がよほど価値があります。
まずは、仕事の必要性があるか?を確認してください。
自分の仕事に合った資格を探す
必要性のある資格は探せば意外とあります。
例えば、『メンタル』『資格』とGoogleで調べると、いくつもメンタルの資格が表示されます。
ページを開くと以下のことが説明されています。
資格を得る事でできる事・わかる事
資格の得方(資格を得るための教材やテストの受け方等)
資格を得る事でできる事が自分の仕事に直結するものかを確認することができます。
決してメジャーな資格である必要はないということ
意外とマイナーな資格でも面接ではそれがネタになって盛り上がることもあります。
仕事に直結している説明ができれば、面接官の好評化につながります。
こちらのサイトでも資格取得についていろいろなアドバイスが掲載されています。
資格の受験方法の確認
さて、自分の勉強したい資格が見つかったら以下の確認をしましょう。
〇勉強の費用
〇テスト受験の費用・申し込みに必要な物
〇雇用保険の『教育訓練給付金』の対処であるか。
何かを学ぶ際は少なからず金がかかります。
テストは『家でテキストを見ながら受験』や『会場で持ち込み不可で受験』等テスト形態は様々です。
申し込みの際、場合によっては学校の卒業照明が必要な物もあります。
また、テストによっては雇用保険からの『教育訓練給付金』の対象であるものもあります。
その資格の勉強をすると、費用の20%が支給されるものです。
テストを受験するための下調べは本筋ではありませんが、大切です。
まとめ

この記事は、専門職として市場価値を上げるためのスキルの上げ方について書きました。
仕事の上では、コミュニケーション力や論理的思考と言った汎用スキルは大切ですが、専門職として価値を上げるには専門スキルは不可欠です。
専門スキルを上げるために資格の取得は非常に良い武器になります。
資格の勉強そのものも実際の仕事で役に立つのでぜひ仕事に合った資格を勉強しましょう。
資格の選び方は、あくまで自分の仕事に直結するものを選んでください。
勉強方法は難易度に合わせて、「独学」「通信教育」「通学」があります。
これはご自身のスタイルに合わせて選んでください。
☟お勧めの勉強方法について以下ブログで紹介しました。興味がある方はご覧ください☟
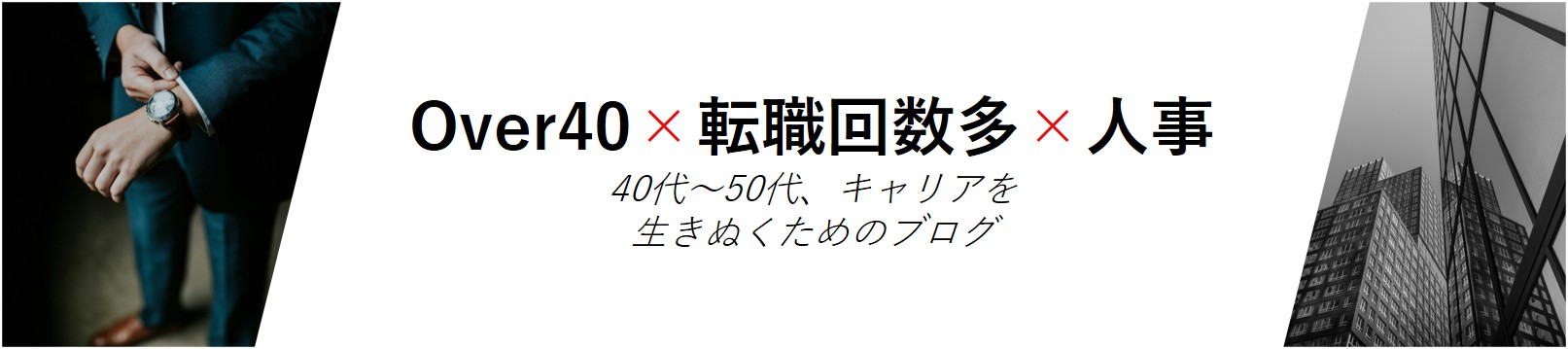




コメント