会社の選考で落ちた時によく『他者比較』と『総合的判断』と説明されますが、そういわれて納得できますか?
モヤモヤのまま次の会社にトライするのはちょっと気持ち悪いですよね。
しかし、人事がどんな時にこの理由を使うかが分かれば一定の理解はできます。
選考する側が何故この理由を使うのかを理解して、この言葉の受け取り方を変えましょう。
次への切り替えがスムーズになります。
今回は『他者比較』と『総合的判断』を応募者目線、人事の目線双方の体験を基に説明します。
採用担当は何故この2つのフレーズを使うのか

会社は何故「他者比較」だったり「総合的判断」を使うのか?
採用をする側の意図は2つ考えられます。
〇様々な要素で比較をしている
〇カルチャーフィット
〇責任回避
様々な要素で比較をしている
採用をする際、人を1つの側面では判断しません。いくつかの項目を点数化します。
具体的には、その会社の基準で、項目を作りそれぞれ点数化します。
例えば以下の例を見てみましょう
Aさん
協調性 5点、 知識技能 3点、 カルチャーフィット 4点 合計12点
Bさん
協調性 3点、 知識技能 4点、 カルチャーフィット 4点 合計11点
このような点数化をした場合、合否の連絡の際、「貴方の協調性は弊社基準得で3点で…」とは説明しません。
結果、「他者比較」や「総合的判断」となります。
カルチャーフィット
点数化できる問題だったり、知識技能のように具体的な内容での比較検討の結果なら説明の余地がありますが、会社の文化が理由でNGを出す時があります。
また、知識・技能で優っている人と劣っている人がいた場合に、カルチャーフィットを優先して劣っている人を合格させる場合もあります。
文化への合致は人により言葉への表し方や言葉からの理解の仕方が異なることや、結局は面接官の感覚でそう思う部分があるから、カルチャーフィットは説明が難しいです。
結果として、「他者比較」だったり「総合的判断」となります。
責任回避
今まで説明のとおり、あくまで評価はその会社の基準で行います。
よって、その会社の評価理由を修正したところで他の会社も同じ評価基準とは限りません。
また、感覚的な印象や文化もあるので、言葉での表現をすることが難しく、逆に言葉の解釈も間違った方向に行くリスクがあります。
企業の面接官の言葉は時として候補者に影響を与える可能性があるため、明言を避けたいのが本音です。
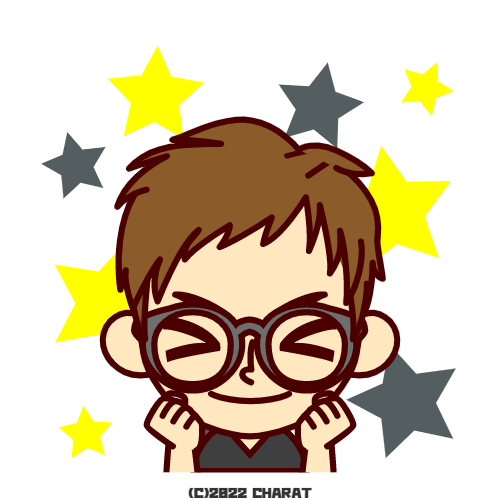
企業によっては、面倒を避けたい。決まり文句を言うことで説明せずに済ませたいという意図がある所もありますけど…。
結果なるべくオブラートに包む意味も込めて「他者比較」「総合的判断」でごまかします。
受ける側の理解の仕方

では受ける側は、その表現のフィードバックをもらったときにどうすれば良いか?
人事で、その表現をしてしまったときの心理を説明します。逆に皆さんは人事の本音はこうなんだ…程度に思っていてください。
返答が遅かった時
人事担当が最後の最後まで迷った時が多いです。
人事の本音はこんな感じです。
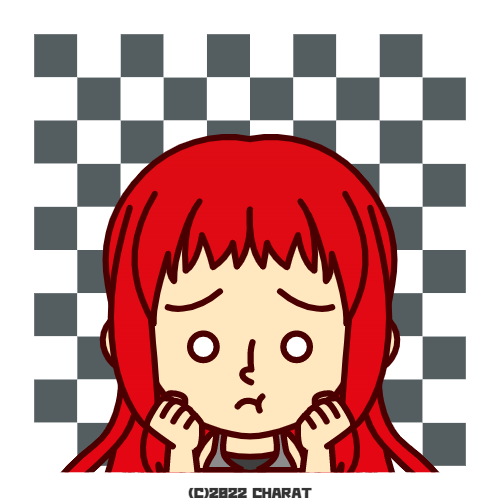
うわ~~~!めっちゃ悩む。双方とも採用したいけど、予算が1名分なんだよね~~~。Aさんの能力を優先するかBさんのカルチャーフィットを取るか?
採用の現場で審査するからこそ思うのですが、「圧倒的勝利」は極めて稀です。100%フィットは非常に難しいです。
角度の違う85%フィットの人が2名、3名なんてよくある話です。
よって返答が遅くて「他者比較」だったり「総合的判断」だった場合は超おしい!と思ってください。
返答が早かった時
シンプルにカルチャーアンフィットまたは、本当に合わなかったのだけど、会社の方で説明を避けたいのだと思ってください。
説明を避けたい理由は傷つけたくなかったり、感覚的な部分で企業文化に合わなさすぎる、または本当に基準に達していない等様々ですが、早く忘れましょう!というサインだと思ってください。
おそらく頑張って入ったところで、いろいろなものが企業と合わずにお互い苦労すると思います。
「下手に変な会社に時間を取られなくてよかった」くらいに考えすぐに他社を探すに限ります。
まとめ

今回は、採用の選考で落ちる理由の中で、最も理解に苦しい「他者比較』と「総合的判断」について書きました。
人事視点でいうと「他者比較」「総合的判断」は
1.選考の際、様々な側面を採点し、合計点を相対評価で比べている。
2.企業文化とのマッチ度で図っているがその説明が難しい。
3.無難に終わらせたい。
の三つの理由で使っていました。
もし、選考結果でこのような理由を言われた際は、よほど競ったか、カルチャーアンマッチで入社したところで良い成果が得られないため、今縁がないことが分かって良しとしましょう。
引きずるのももったいないので・・・。
「なぜ落ちたか?」をどうしても知りたいという方は、エージェント経由で応募することをお勧めします。
参考になるエージェントは別の記事で準備しました。参考にしてください。
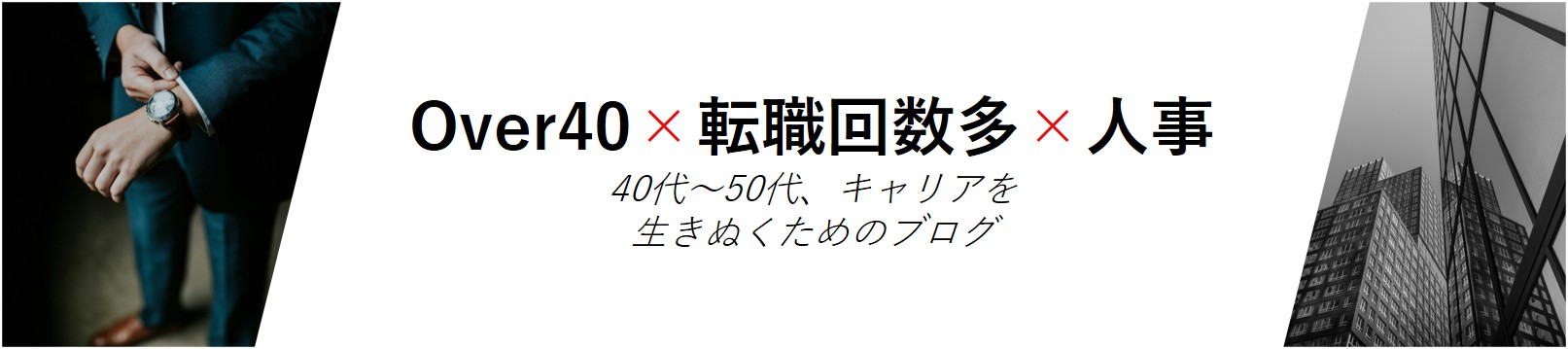
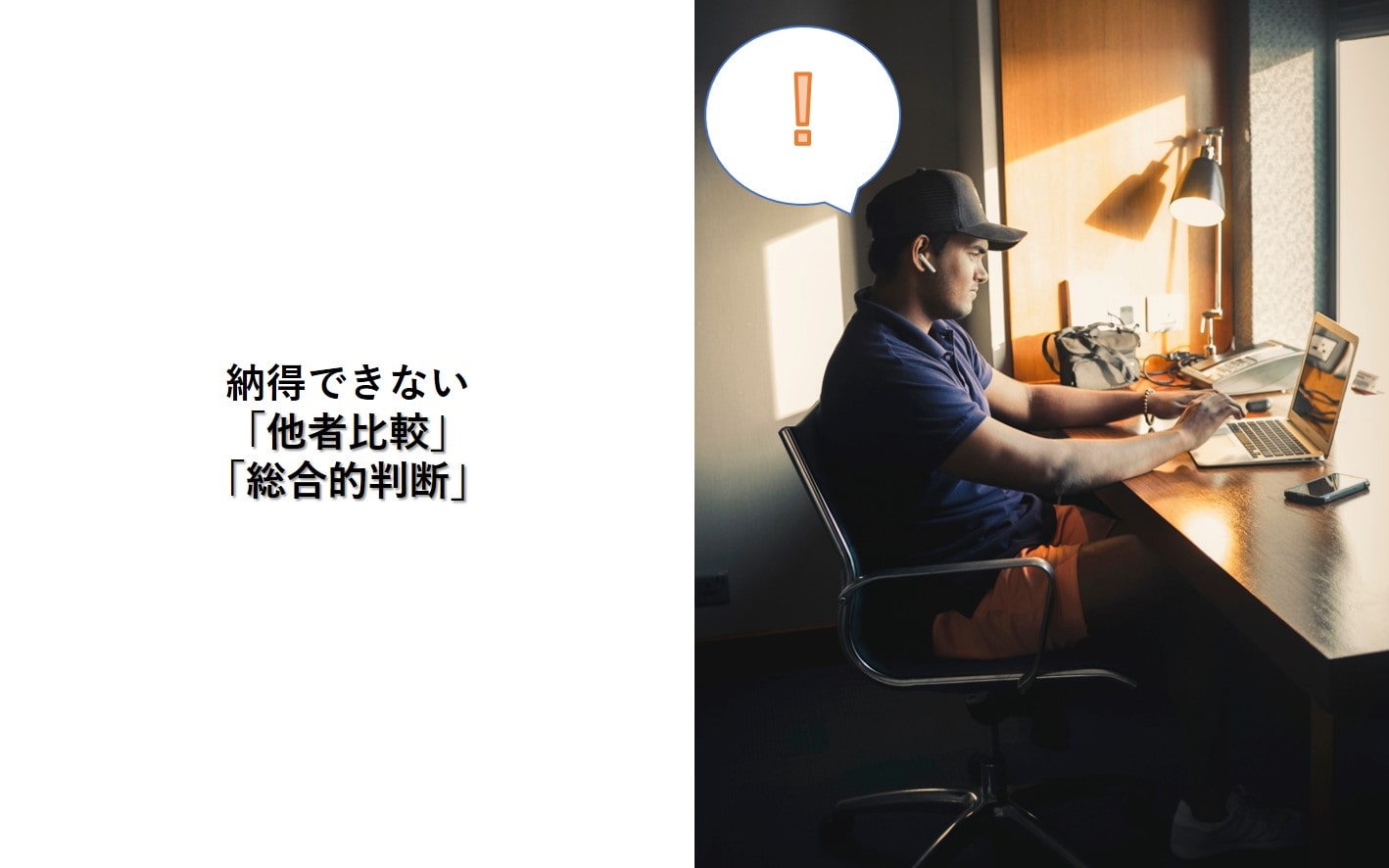



コメント