そんな悩みを抱えている中小企業の経営者や人事担当の方、多いのではないでしょうか?
実は、人事制度は“自社で”創ることができます。
むしろ、自社で創ったほうが、現場にフィットした、実効性の高い制度になることも多いのです。
この記事では、人事制度の自社構築の必要性とそのやり方についてお伝えします。
コンサルに頼らない理由

まず最初に誤解のないように言っておくと、コンサルタント自体を否定しているわけではありません。
専門知識や客観的な視点を提供してくれる、非常に有益な存在です。
しかし、人事制度は「運用してナンボ」。
外部の専門家がどんなに立派な制度を作っても、現場に馴染まなければ形骸化してしまいます。
制度を形にするのは社員自身であり、制度を育てていくのも社内のメンバーです。
自社で創るメリット
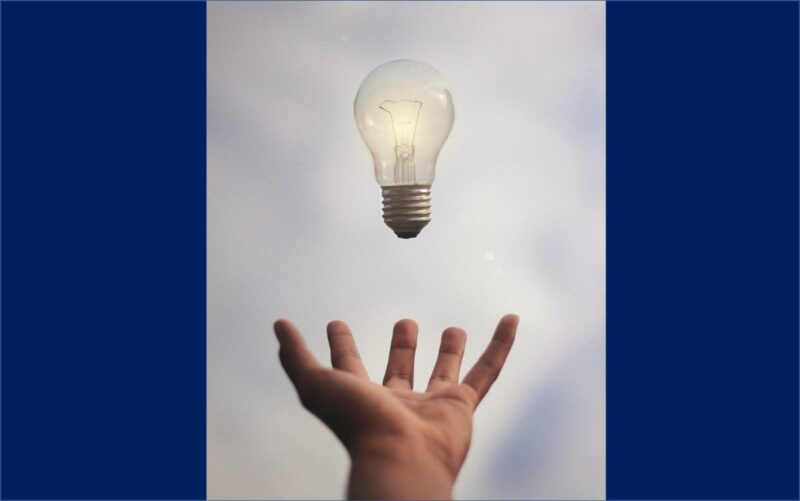
1. 現場に合った制度設計ができる
業務内容、企業文化、社員の価値観、評価者や社員の人事制度の熟練度。
これらは会社によって千差万別です。
自社で制度を作れば、会社に一番合った人事制度が設計できます。
コンサルタントは常に「最先端」の制度を用意します。
しかし、必ずしも「最先端=自社の最善」ではありません。
例えば、目標管理制度。
今一番ポピュラーな制度ですが、「自ら目標を立てる事」はどの職種にも共通していますか?
工場の方や、事務の方は具体的な目標を立てる事は困難です。
コンサルタントは、「最先端ありき」で進めることが多く、結果疎遠な制度になる事が多いです。
一方、社員が自分たちの感覚で、良い悪いの先入観なしで作った制度は社員から使い勝手の良いものに。
自社で作るメリットの1つ目は現場に合った制度設計ができる事です。
2. 社員の納得感が高まる
制度作りのプロセスに社員を巻き込むことで、「自分たちで作った制度」という意識が芽生えます。
結果、制度に対する理解と納得感が高まり、運用もうまくいきやすくなります。
人事制度は運用が命、どんなに良い制度を作っても現場が動かなければ意味がありません。
その中で、現場に浸透する制度は、設計段階から巻き込むことが一番です。
素人が作っても…と言う意見もありますが、1人の専門家がガイドをすることで解決可能!
むしろ、その素人に作ってもらったほうが、使用する人のレベルや志向に合った制度作成ができます。
社員の納得感を高める為にも人事制度は自社設計が有効です。
3. 柔軟に見直し・改善できる
運用してみて初めて見えてくる課題もたくさんあります。
しかし、運用するのは現場の方々。
プロが作った借り物の制度では、何が良くて何が悪いのかすら分かりません。
自社で作った制度なら、自分の意図と違うかもわかるし、自分事として問題を認識、改善もスピーディに!
改善等についても自社設計は基本です。
自社で制度を創るためのステップ

「自分で人事制度を作るなんて無理…。だからコンサルに頼むしかないです」と思う方、実際多いです。
確かに、自分たちだけで制度設計をするのはハードルが高く感じますよね。
法令や社内の整合性、社員の納得感…考えることはたくさんあります。
でも、実は人事制度づくりの工程そのものは、どの会社のコンサルタントが入っても大きく変わりません。
いわば「手順」があるのです。
人事制度ができあがるまでの手順を、ざっくりご紹介してみますね。
1.現状の課題を洗い出す
2.目指す姿を明確にする
3.制度の基本方針を決める
4.社員参加で制度設計
5.プロトタイプを作って試す
現状の課題を洗いだす
今の制度のどこに不満があるのか、何がボトルネックになっているのかを把握しましょう。
人事制度は「社員にどう働いてほしいか」「組織としてどう成長したいか」という経営の意図を形にしたものです。
しかし現状、評価や昇給の仕組み、職務の定義等現場と経営の意図にズレがあると、制度がうまく機能しません。
課題を洗い出すことで、「どこにズレがあるのか」「本来あるべき姿と何が違うのか」が見えてきます。
まずは現状の不満やボトルネックを事前に拾っておきましょう。
現状の業務フロー・責任範囲・人材の層・組織文化を把握することも大切!
制度設計の際にそれを反映させることで、より「社員が使える制度」が作れます。
目指す姿を明確にする
人事制度は経営ビジョンと密接に関係します。
目的をはっきりさせることが第一歩です。
実際いくつかの会社で、人事制度を作成しましたが、多くの会社は、この部分が欠如していました。
形骸化している会社は大体、『社員にどうなってほしいか? 』『どういう行動をとってほしいか?』が曖昧な場合。
目的がない制度はあまり意味がありません。
ミッション・ビジョン・クレドから作成した会社は、目指すところが明確なため設計はしやすく、一貫性がありました。
人事制度の目的は明確にしておきましょう。
制度の基本方針を決める
制度の基本設計とは「企業の理念や成長戦略に沿って、人事の軸を定めるもの」です。
制度は何を実現するためのものかを整理します。
具体的な例を挙げると、「成長促進」、「公平性の確保」、「採用競争力アップ」等。
そして「うちの人事制度は何を大切にするのか」を明文化します。
例えば、以下のような感じです。
「わが社の制度は個々の成長を促す為、結果だけではなくプロセスも評価します。」
「わが社は、成果主義の会社です。その為あくまで成果のみ評価対象とします。」
勿論この方針に沿って人事制度を作成する為以下が非常に大切になります。
経営者の腹落ちは最重要!トップの考えと制度がずれていると運用が形骸化します。
「頑張り」等あいまい表現は厳禁!明確な言葉を使い評価軸と制度の関係性まで見据えると良いです。
作成する個々の制度との一貫性は重要。ずれてしまったら軸のない制度に仕上がります。
基本方針の策定は人事制度の軸を作る事です。
社員参加で制度設計
評価制度、等級制度、報酬制度、それに伴う育成計画等、人事制度の柱となる部分を設計します。
できるだけ、現場主体で作りましょう。
HRも現場の意見を優先して制度を設計します。
できるだけ多くの選択肢を用意して、現場の代表者の総意を採用します。
その際、より「最新な物」や「今正解とされているのも」に誘導したくなりますが、それは禁止!
あくまで「使う側」が基本方針を全うできるツールとしての人事制度であることが正解です。
最先端なものは必ずしも、使う側のレベル感や需要とマッチするわけではありません。
むしろ「もう古い」とされていたものが基本方針と照らし合わせてもマッチすることも往々にしてあります。
制度はなるべく現場主体で作りましょう。
なお、注意として…経営者とのみ作ると、かなり「ワンマン」なものになるため、人事制度を作る効果は薄いです。
プロトタイプを作って試す
人事制度を作成したらすぐ「実行」は危険です。
どんなに対策を練っても実行したら予想できない穴があることが多いから。
一旦プロトタイプとして実戦で試してみましょう。
一度に完璧を目指さず、小さなチームから試行導入して、徐々に全社展開するのがおすすめです。
現在人事制度を運用している場合は、併用して運用してみて、その有効性を確認することもお勧め。
実践の前に試してみましょう。
~まとめ~人事制度は「進化する仕組み」

完璧な人事制度を一度で作ることはできません。
重要なのは、「試して、見直して、改善する」というプロセスを繰り返すこと。
そのためには運用する自社社員の制度に対する理解・自分事の意識は不可欠。
社内で制度を創る文化が根づけば、外部に頼らずとも、会社は自ら進化できる力を持ちます。
「人事制度は会社の設計図」
それを自社で描けるようになれば、組織はもっと強く、もっとしなやかになります。
でも、「素人に人事制度は作れない!」と言う方の為に手順も紹介しておきました。
参考にしてみてください。
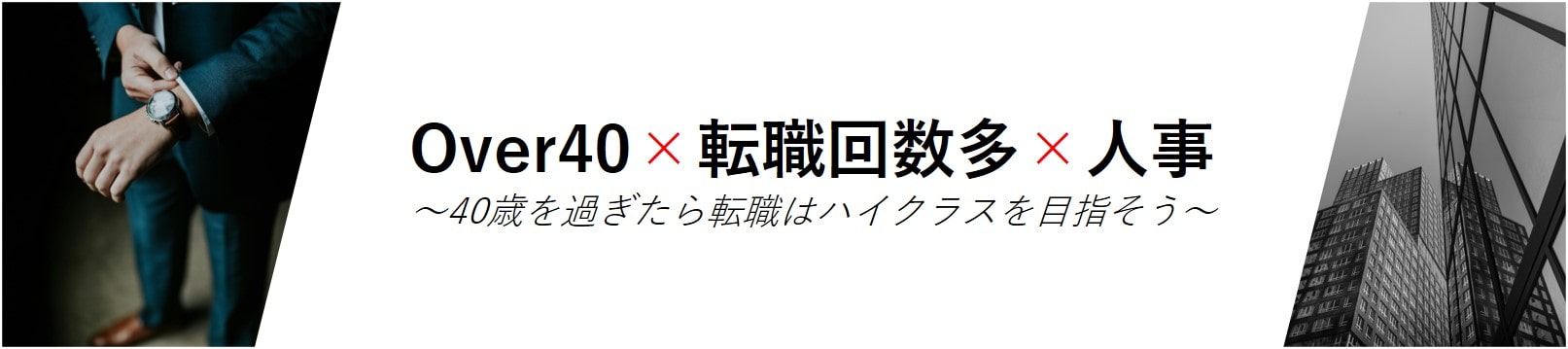
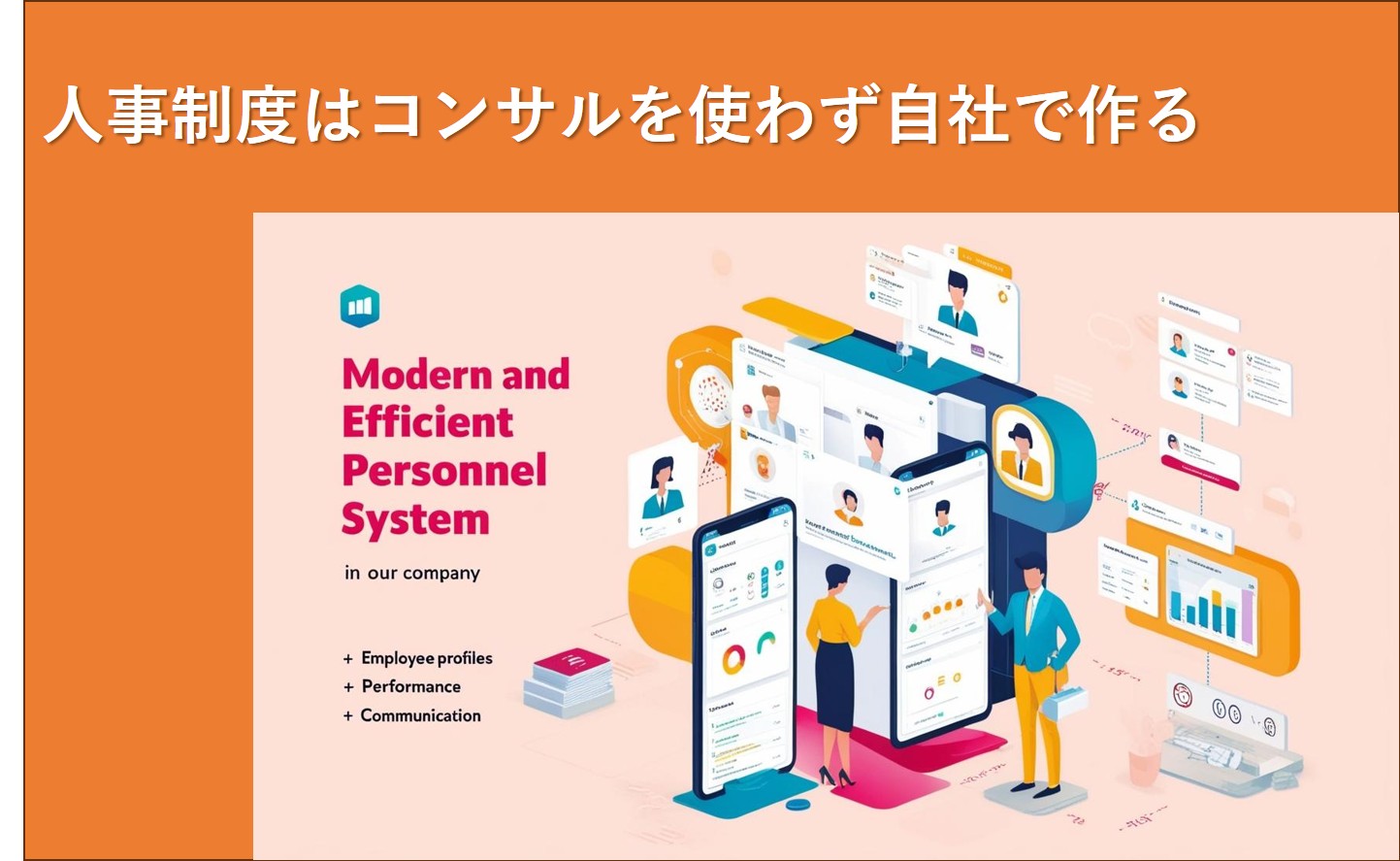


コメント